こんにちは。
「書いている人」@CPABlogです(プロフィールはこちら)。
突然ですが、あなたが今監査法人を辞めたら退職金はどれくらい貰えるか知っていますか?
この質問に答えられる同業者の方は、意外と少ないのではないでしょうか。
私も知らなかったので、事務所の規程を確認してみました。
シニアマネージャまでは順調に昇進してきたのですが、私程度の評価ではパートナーにはなれず、事務所で苦しい立場に追い込まれてしまっています。
間もなく事務所を去ることになると思いますので、「退職に関わるお金の話」をまとめておきたいと思います。
監査法人を辞めたいと思っている会計士の皆さんの参考になれば幸いです。

退職金
私はシニア時代に一度、大手監査法人を退職し、別の大手監査法人に転職しています。
その時の退職金は百万円ちょっとでした。
当時は若く、転職後もバリバリ働くつもりでしたので、退職金の金額など気にもしていませんでしたが、今回はそういうわけにはいきません。
監査法人でズルズル働いてしまった私は、年齢的に今回の転職で年収が上がることは望めませんので、退職金がどれくらい貰えるのかは、大事な話です。
そこで事務所の退職金規程を調べてみたのですが、計算方法は以下のようにシンプルなものでした。
退職金=基準金額×勤続年数
基準金額は自己都合退職の場合、スタッフで25万円、シニアで30万円、マネージャで35万円、シニアマネージャで40万円です。
例えば、9年間務めた(スタッフ3年、シニア4年、マネージャ2年の合計9年間)場合の退職金は265万円(25万円×3年+30万円×4年+35万円×2年)となります。
私の場合は、今の法人に来て10年ちょっとなので、退職金は四百万円前後といったところです。
どうでしょう。
もっと少ないのかと思っていましたが、意外とありました。
定年まで勤めたらいくらになるのか計算してみようと一瞬思ったのですが、定年まで働けない職場なので辞めようとしていることを思い出し、やめました。
なお退職金の計算方法は、法人によって異なると思いますので、正確な金額を知っておきたいという方は、事務所のポータルサイトなどに掲示されている退職金規程などを確認するようにしてください。

企業年金基金
監査先の退職給付制度はよく理解しているが、自分の事務所の制度は全く理解していないという同業者の方が多いのではないでしょうか。
私も担当しているクライアントの退職給付制度は良く知っているのに、自分の事務所の制度は全く知りませんでしたw
今勤めている監査法人は、企業年金基金にも加盟しているようです。
いわゆる年金制度の三階部分ですね。
こちらの給付金が一時金相当で二百万円近くあるようです。
これまで意識していなかったものなので、ちょっと得した気分になりますね。
転職先が公認会計士企業年金基金に加入していれば、引き続き公認会計士企業年金基金に入り続けることになります。
シニア時代に転職したときは、大手監査法人から大手監査法人への転職だったので、このパターンでした。
今度は一般事業会社等への転職となりそうなので、公認会計士企業年金基金からは一回脱退することになり、転職先で加入している基金等があれば、そちらの加入することになります。
脱退の手続きは事務所が行ってくれるようですが、給付金の受け取りや移管に関しては、退職後に個人で手続きを行う必要あるようです。
私の場合は加入期間が10年を超えていますので、
- 給付金を移管
- 一時金で受け取る
- 給付を繰り下げる
のいずれかを選択することになるようです(加入期間3年未満は給付なし、3年から10年は一時金として給付or移管のみ)。
給付を繰り下げた場合は、2%で運用してくれるようです。
今のところ資金的には困っていませんので、これについては給付を繰り下げ、年金として受け取るという選択が良さそうです。

協会への登録費用
監査法人では、当たり前のように事務所が負担してくれているので意識することはありませんが、実際には年間で本部会費6万円、地域会費4万2千円(東京の場合)の合計10万2千円の登録費用を支払っています。
転職に当たっては、この登録費用の負担について、転職先と交渉しておくことが必要です。
転職先でも資格を使って業務を行うなら、交渉次第で会社が費用を負担してくれると思います。
一方で、業務上資格維持が必須ではない場合は、負担してくれない場合が多いようです。
この場合、一旦登録抹消するのも一つの方法だと思います。
登録抹消では、資格を失うわけではありませんので、いつでも再登録可能です。
年間で10万円程度とそれなりの負担となりますので、転職先で費用を負担してもらえないなら、一旦登録抹消するのも一つの方法だと思います。
なお登録抹消の手続きにも、公認会計士・監査審査会の審査が必要です。
通常は、申請して実際に登録抹消するまで1か月くらいかかるようです。
事務所によっては、退職時は変更登録しか受け付けてくれず、登録抹消を行う場合は、個人でやらなくてはならないケースもあるようです。
この場合は、登録抹消の手続きが完了するまで、会費等を徴収されることになるので、注意が必要です。
一般事業会社等へ転職し資格維持が必要でない場合は、有給休暇消化中にでも登録抹消の手続きを行うのが良さそうです。
なお登録抹消に必要な提出書類等は公認会計士協会のサイト上には掲載されておらず、協会に電話やメール等で直接連絡して請求する必要がありますので注意してください。

失業給付
失業給付ですが、公認会計士であっても要件に当てはまれば受給することが可能です。
給付額は退職前の給与を基準に計算されるのが原則ですので、会計士は高額となることが少なくありません。
ただし上限額が設けられているので、勤続年数が1年以上10年未満の自己都合退職の人で、総額70万円程度の失業給付を受給することが可能です。
過去には士業の人は登録を抹消しないと失業給付は受給できなかったこともあったようですが、現在は登録の有無は無関係となっています。
このように会計士でも利用しやすくなった雇用保険制度なのですが、これから監査法人を辞めようと考えている方は、失業給付のことは考えないほうがよいと思います。
なぜならキャリアにブランクは生じさせないほうが良いからです。
キャリアにブランクがあると、面接等では必ずその期間に何があったのか問われることになります。
これに対して離職期間の説明をうまくするのはなかなか難しいので、初めからブランクは作らないようにすべきです。
なお独立開業を目指して退職する場合は、失業給付は受給できません。
これは雇用保険制度が求職していることが前提の制度で、開業準備期間中は求職中とはみなされないためです。
失業給付を受給するときは、不正受給とならないように注意することが必要です。

住民税、社会保険料
監査法人を退職して独立開業する場合は注意が必要です。
住民税の納付は翌年度となるため、監査法人を退職した後、多額の納付が必要となることを理解しておく必要があります。
開業直後は収入が少ないのが一般的です。
そんなときに前年度所得に基づき計算された住民税の納付が必要となりますので、退職前にこれらの資金は確保しておかなければなりません。
また健康保険についても、注意が必要です。
国民健康保険に切り替えた場合、保険料は前年度所得に基づき計算されます。
そのため開業直後の苦しい期間でも、多くの保険料を支払わなくてはなりません。
またそれを避けるために、組合健保への加入を任意継続する方法もあります。
ただし任意継続する場合でも、事務所負担はなく全額自己負担となりますので、以前よりずっと多くの保険料を支払うことになります。
独立開業を目指す場合は、これらの支出についてもきちんと備える必要があります。
なお転職する場合は、もろもろの手続きは転職先の人事で行ってくれるので、特に意識する必要はありません。

賞与
別の記事で書いたのですが、監査法人を円満退職するなら、最終出勤日は6月末とするのがベストです。

これなら6月支給の賞与は問題なくもらえます。
ただし賞与支給額の前提となる評価については、下げられてしまうケースもあるようです。
賞与の支給対象期間を考えれば、退職が予定されている事実だけをもって評価を下げられることは不当な扱いだと思います。
でも賞与は職員たちの仕事に対するモチベーションを維持させる有効な手段であることを考えれば、辞めることが決まっている職員の評価を下げて、他の職員の賞与の原資とすることは、仕方ないことなのかもしれません。
ちなみに私がシニア時代に転職したときは、評価を下げられることはなかったのですが、次はどうなることやら。

まとめ
監査法人を辞めることによって、それなりにまとまった金額のお金が手に入ります。
ただし当たり前の話ですが、これらは将来受け取るはずの退職金の前払いを受けているに過ぎません。
次の仕事を決めて監査法人を辞めさえすれば、お金に困ることはありません。
一時的に手に入るお金は、将来のために大事に取っておきたいと思います。
監査法人でもらえる退職金が気になった人は、以下の記事もどうぞ。

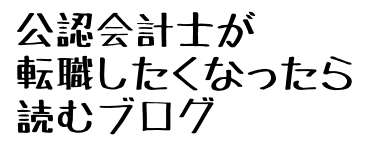


コメント