こんにちは。
「書いている人」@CPABlogです(プロフィールはこちら)。
監査法人で働く皆さんの中には、法人内のバックオフィスの仕事に興味を持たれている人もいるのではないでしょうか。
私はシニア時代にバックオフィス系部署で二年間働いた経験があります。
当時、監査に飽き始めていたこともあり、新しいことを探していた時期でもありました。
そんな時、何気なく事務所のポータルサイトを見ていて、とあるバックオフィス系部署の募集が目に留まったのです。
数日考えた末、パートナーに相談したところ、いい経験になるとあっさり異動が決まり、繁忙期明けからバックオフィス系部署で働くことになったのでした。
バックオフィスの仕事を経験した会計士はそう多くはないと思います。
今日はその時の経験をもとに、バックオフィスの仕事を掘り下げてみたいと思います。

監査法人のバックオフィスの仕事
監査法人のバックオフィスの仕事には以下のようなものがあります。
審査部門
監査でインチャージを経験している人なら、審査部門と接点を持ったことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
私は審査部門の人たちには何度もいじめられた経験があります(笑)
審査部門は審査担当社員を統括するとともに、重要審査事項について審査会などの会議体で審査を実施するなどして、監査チームが出す監査意見の適切性を担保するために設けられている部署です。
審査は意見表明に先立ち実施される事前の審査のみならず、リスクの高いと思われる会社を選んで実施する事後の審査も行われています。
審査部門で誤った判断を行うことによって、法人が消滅してしまうような事態を招くこともあるため、審査部門には監査に精通した会計士たちが集まっています。
監査チームが実施する監査の適切性をチェックする業務なので、スタッフやシニアはおらず、マネージャやシニアマネージャクラスの会計士たちが下働きで見かける程度で、主要な業務はパートナーたちが担当しています。
切った張ったの世界である審査部門に長年いるパートナーたちの目つきが悪いと感じるのは、私だけでしょうか。
品質管理部門
品質管理では監査マニュアルや監査ツールの開発や改訂を行ったり、監査チームからの会計処理や監査上の対応などの事前相談を受け付けたりしています。
監査マニュアルや監査ツールは基本的にグローバルメンバーファームで使用している監査マニュアルや監査ツールを利用しているのですが、日本の監査基準や法規制と整合しているとは限らないため、日本の監査基準や法規制に合わせるためのローカライズ作業が必要となります。
そのためこれらの業務を担当する会計士は、グローバル監査マニュアルに精通しているとともに、日本の監査基準や法規制にも精通していることが必要です。
またグローバルで利用しているマニュアルの改訂があるときは、何か月も前から各メンバーファーム間で意見交換を実施しており、深夜の時間帯に現地と電話会議を行ったりしています。
電話会議は英語で行われますので、これらの業務を担当する者は英語力が必須となります。
教育研修部門
監査法人の人材育成を担っているのが教育研修部門です。
東芝事件を契機に監査の品質問題にスポットがあたり、監査に携わる人材の育成の重要性が増しています。
また試験に合格したばかりの新人会計士を一人前のプロフェッショナルに育成するためのプログラムを考えるもの教育研修部門の仕事です。
情報の鮮度が重要な研修は、ライブで実施されることもありますが、最近はネットで配信されるe-Learningが増えています。
これらのe-Learningの研修プログラムを企画、制作するのも教育研修部門の仕事になります。
審査部門や品質管理部門で働く会計士はそれなりにいるのですが、教育研修部門で働く会計士の数は決して多くはありません。
研修プログラムの企画は、業界の動向を理解している必要があるため、会計士が行う必要がありますが、コンテンツの制作等は外注先を利用することになるので、必ずしも会計士が行わなければならない業務でもありません。
そのため研修プログラムの企画やコンテンツのチェックはパートナーが担当していることが多く、これらの部署で働いているシニアやマネージャーの数は多くはありません。
総務、経理、人事部門
一般事業会社で見られる総務や経理、人事といった部門も当然ながら監査法人にもあります。
ただしこれらの業務を公認会計士が担当することに意味はなく、無資格の事務職に業務を担当させ、それらをコントロールするためにパートナーが管理を行っているケースがほとんどだと思います。
監査法人の経理や人事、総務をやりたいと思う会計士もほとんどいないと思いますが、これらの業務をやりたいと思うなら、パートナーになって法人のマネジメントを担当する立場にならなければなりません。
経営企画部門
監査法人においても経営企画部門はあります。
ただし一般の職員が希望しても配属されることはありません。
将来を有望視されている若手パートナーたち数名が事業の創出やリソースの配分など法人のかじ取りを企画し、経営を執行するパートナーたちに上申するのが主な業務で、誰でもができる仕事ではありません。
監査法人の経営企画に携わりたければ、最低限パートナーになることが必要であり、パートナーになった後にさまざまな成果を出して評価されなければなりません。
IT部門
ネットワークやサーバー、貸与PCやスマホの管理やユーザーサポートを行っているのが、IT部門です。
これらの業務も会計士が担当する意味なく、専門の職員が業務を担当していることがほとんどです。
ただし専門職員たちの業務のコントロールは、ITに詳しい会計士が行っていることが多いようです。
一方でITに関する企画系の仕事は会計士が担当するケースもあります。
グローバルで開発された監査ツールを日本でも利用するためにローカライズが必要になるのですが、これらの作業には監査の知識も必要になるため、ITに詳しい会計士が担当することが多いようです。
法人によって担当する部署は異なるようですが、品質管理部門内にIT担当が置かれている法人もあるようです。

チャンスがあれば異動すべきか
私はシニア時代に、とあるバックオフィス系の部署で二年間働きました。
監査に飽き始めていた時に、たまたま募集を見かけたのがきっかけでした。
その二年間で監査法人のマネジメントに携われたのは貴重な経験だったと思います。
でも今はチャンスがあってもバックオフィス系の部署へは異動すべきではない考えています。
監査法人でバックオフィス系の仕事をしていると、たくさんのパートナーたちと協働することになります。
一緒に働いた若手パートナーの中には、現在の法人の経営執行の主要なポジションに就かれている人もいます。
そう考えると、バックオフィスの仕事で成果を出すことは、監査法人での出世の登竜門なのかもしれません。
でも職員としてこれらの部署で働いていた会計士たちで、出世した人を私は知りません。
バックオフィス系の部署で働く会計士たちの多くは、コミュニケーションが苦手だったり、チームワークができなかったり、クライアントサービスに向いていない人が多かったように思います。
当然ながらこれらの人たちが、監査法人の経営の中枢に昇り詰めていくことはあり得ません。
監査法人で出世していく人は、これらの職員をうまく使って、成果を出していった若手パートナーたちなのです。
もしバックオフィス系の仕事に興味があるなら、一刻も早くパートナーになることを目指すべきです。
そしてパートナーになってから、これらの仕事に関与して、成果を出すことを目指すべきです。
そうすることによって、私がこれまで見てきた若手パートナーと同様に、監査法人の経営の中枢に昇り詰めることができるかもしれません。

有名人も冷遇されていたのは有名な話
さまざまなメディアで会計基準等の解説を発信しているOさんですが、その活躍とは裏腹に、出世は遅かったようです。
私も一度お会いして挨拶を交わしたことがあるのですが、物静かな学者タイプの方でした。
それゆえ、クライアントサービスには向いておらず、仕方なしに品質管理部門の片隅に席を設けてリサーチ業務をやらせたのが始まりだったとか。
メディアでの露出が増加していく中、なぜパートナーではないのかという外部の声に押されて、パートナーに登用されたというのは有名な話です。
監査法人で出世したいなら、クライアントサービスから軸足を移してはいけません。
バックオフィスはコストセンターでしかありませんので、よほどの成果を上げない限り、評価されることはありません。
それよりもプロフィットセンターであるフロントの仕事で成果を出した方が、圧倒的に出世は早くなります。
このことを忘れてはいけません。

まとめ
バックオフィスの仕事は重要な仕事だし、面白い仕事もたくさんあります。
でも対人関係をうまく築けないなど、クライアントサービスに向いていない人たちの逃げ場になっているのも事実です。
パートナーになれずともバックオフィスの仕事で定年まで働けるなら、悪い話ではないとも思います。
でもリーマンショックの後のリストラで、一番最初に声が掛かったのが、このような人たちであったことを忘れてはいけません。
パートナになれない普通の会計士が、定年まで働ける安住の地は監査法人にはありません。
バックオフィス系の部署で働くことを考えるくらいなら、外の世界で活躍する方法を模索すべきだと思います。
そうでなければ、私と同じように40代になって監査法人で居場所を失うことになってしまいます。
自分も監査法人でパートナーにはなれないと思った人は、こちらの記事もどうぞ。

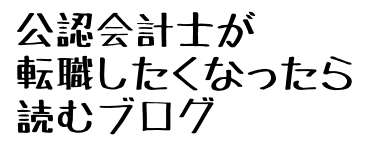


コメント